先輩と後輩
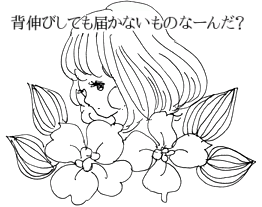
六年 立花仙蔵 潮江文次郎 七松小平太 中在家長次 食満留三郎 善法寺伊作 五年 四年 三年 神崎左門 次屋三之助 立花先輩と! 私と立花先輩以外居ない部屋の中は静かで、先輩が時々本の頁を捲る音が響くだけだった。 一向に現れる様子のない作法委員所属の後輩達を探し、私は何度目になるのか分からない視線を戸の方に投げた。 暇つぶしにと始めた化粧箱の整理は、もう終わりに向かっている。きれいに磨きあげた鏡はぴかぴかと光っているし、紅 や白粉が溢してあった箱の中はきれいに磨き上げられていた。手に持った布巾を桶の中に浸すとじわりと紅の赤色が水の 中に染み出す。顔の向きは桶に向けたまま視線だけを動かし、立花先輩を盗み見る。先輩は一向に現れない後輩に怒る様子もなく、本の中の文字を ひたすらに目で追っていた。聞けば今日の集まりは、たいして重要な用というわけではないらしいのだ。そんなことを知る 由もない私は掃除当番の仕事を大急ぎで終わらせこの部屋に駆け込んだのだが部屋に居たのは立花先輩一人で、その上に その最初の言葉は「早いな」である。 「...い、急いで、来ました、から」 息も絶え絶えに答える私に先輩は少し楽しそうに表情を変化させた。 「そうか。ゆっくり来てくれてかまわなかったのだがな」 さらりと髪を揺らし涼しげな表情を浮かべる先輩に対して私はというと見苦しいほどに息を弾ませている。何だか今更に 走ってまで急いで来た事がバカらしく感じて小さく溜息を吐いた。 それから先輩は適当にくつろげと言うので、最初はぼんやりと座っていたのだが、何もせずに居る時間が惜しくなって化粧 箱の掃除を始めたのだ。だが、その掃除ももう終わってしまった。桶の水を捨てに行き、手を洗い戻ってくるも部屋の中に はやはり立花先輩しかいなかった。「おかえり」と掛けられた声に「ただいまです」と返しながら、一体いつになったらあいつ らは来るんだ。胸の中で愚痴りながら化粧箱の中に化粧道具を詰めていく。乱雑に詰め込まれていた化粧道具を出来る限り きれいに並べる。ついでに中身が少なくなっている物は書き留めておこうと思い、筆と紙を仕舞ってある引き出しから取り出し 、書いていく。 これで次に優先的に買わなくてはいけない物が分かるだろう。 淡々とした作業を一心に行っているとすぐ後ろに気配を感じた。驚き振り向くと、すぐそばに立花先輩の顔があり、また驚く。 「ほぅ、きれいになったじゃないか」 私の様子なんて気にも留めない様子で先輩の視線は化粧箱へと注がれている。耳元で聞こえる声に体を強張らせるも、 先輩は気づいていないようだった。 「そうでしょう」 ちょっと得意になって答えると「調子に乗るな」と頭を軽く小突かれた。大して、というよりも全然痛くなかったのだが 反射的に「いた」と答える。すぐ傍にある先輩の顔は薄く笑みを浮かべていて上機嫌だ。それから先輩はかがんでいた 体制から背筋を伸ばし真っ直ぐの姿勢で立った。 「それじゃあ次の仕事を頼んでもいいか」 仕事なんてあったんですか? そう思いながら何度か目を瞬かせると、あぁ。と先輩は口角を上げにやりと笑った。 その笑みに嫌な予感がして薄く目を細めて先輩を見る。すると先輩は私が何を考えているのか分かったのか心外とでも 言いたげに眉を寄せた。その反応がわざとらしくてますます予感は強くなる。 「なに、簡単なものだ」 「...本当ですか?」 「私が嘘を付くと思うか?」 思います。と答えそうになるが、そんなことを言えばどうなるか作法委員会に所属していれば良く分かっている。なので口 を噤み無言を貫くことにした。だが無言でいる事が答えなので先輩は、失礼な奴だ。と大して気にした様子も無く呟いた。 「だが、今回は本当に簡単なものだ」 「...そうですかぁ?」 半信半疑な私の返答に先輩は無言で鋭い視線を向けてくる。 「そこに胡坐をかいて座ってくれるだけでいい」 「胡座?」 あごをしゃくって早く座れと急かす先輩に逆らえるわけも無い私は黙って正座をしていた足を崩した。 これだけでいいのだろうか? よく分からないままに立花先輩を見上げると、満足そうに一つ大きく頷いた。全くわけが分からない。 「ほら、手が止まっているぞ」 掃除の続きをしろと暗に言っているのは分かったので、わけが分からないままにまた箱の中に化粧道具を詰めていく。 一体なんなんだ。綾部はわけが分からないと思う時が多々あるのだが、立花先輩はそんなことないので一層おかしく感じる 。これがもし綾部だったなら、はいはい。で終わったのだろうけれど相手は立花先輩だ。もしかしたら何か...絞め技なんかを かけられるんじゃないだろうか...と考えると後ろが気になってしょうがない。 耳の神経を集中させ、後ろの様子を探ると畳を擦るような音がしている。後ろを振り返りたくてしょうがないのだが、掃除 を続けろと立花先輩は言ったのだから後ろを向けば怒られてしまいそうだ。 その時だ、背中に大きなものが圧し掛かってきた。驚きながら振り向くと、立花先輩が私を背もたれにして座っていた。 手には本を持っていて今から読書をしようとしているのが分かる。 「...って! 何してるんですか!」 顔を顰めた先輩が嫌々という風にこちらを振り返る。ぴったりとくっついた背中のせいで距離が異常に近い。 前屈みになって少しでも先輩から離れようとするが先輩は私の背中にもたれているので、当然離れるわけがなかった。 先輩の背筋は伸びる事になり、変わりに私にさっき以上の重みが加わることになった。 「重いですよ!」 「お前が自分で自分に負担をかけたんだろうか」 呆れた物言いに言い返してやりたいところなのだけど全くもってその通りなので言葉を喉に詰まらせる。それから先輩は 「今から読書をするから邪魔をするんじゃないぞ」と私に言い含め、本を捲った。 「もしかして次の仕事って...」 一向にそこから動く気配の先輩を横目に見ながら呟く。 「そうだ。私の背もたれだ」 さも当然というように答える先輩は指を動かし、次の頁を開いた。やはり私の嫌な予感は当っていた。誰が好き好んで人の 背もたれになりたがるものか! それなのに先輩は私が背もたれになりたがっているとでも思っているのか、移動する様子 を見せずに流れるように書かれた文字を目で辿っているようだった。だが、ここで抗議をしたとしてもだ、立花先輩が相手 なのだから却下されるのは目に見えて分かっている。すると変に先輩を刺激したり不機嫌にさせてしまうよりは黙って耐えて いた方がいいだろう。何て物分りのいい後輩なんだ...。無意識に小さく溜息が出てきた。 「...なんだ、嫌か」 当然背中がくっついているのだから先輩には私が溜息を吐いたのが分かったのだろう。しまった、と思っても後の祭りだった。 「...そりゃ、まぁ」 出来るだけ穏便に事を進めようと控えめに答えたのだが、重みと熱を感じていた背中からそれらが消えた。 恐る恐る振り返れば立花先輩が片膝を立て座っていた。本にはもう視線を落としていない。真っ直ぐに私を見ている。 「足を崩せ」 「...はい」 よく分からないままにまたしても命じられる。先輩の表情は怒っているようには見えないが、だからといって機嫌が抜群に いい、というわけでもなさそうだ。足を崩し、所謂横座りという格好になると先輩は小さく頷いた。 それから寝転び、私の膝の上に頭を乗せた。 「わぁー!! 何してるんですかっ!!」 何故か私の膝に頭を乗せ、読書を再開させようとしている先輩に向かって叫ぶ。恥ずかしくて今すぐにでも先輩の頭を膝から 落としてやりたいところだが、今までにされたあれやこれやを考えると体は思うように動かなかった。緊張して足に異常に 力が入る。 「お前が背もたれは嫌だと言ったのだろうが。だから、枕に格上げしてやったんだ」 背もたれよりも枕の方が格上だったとは知らなかった...なんて、どうでもいい感想が浮かんできたがそんなことよりも一刻も早く 膝の上からどいて欲しくて下にある先輩の顔をじとりと睨む。すると先輩は心底楽しそうに笑みを浮かべた。 楽しそうと言ってもにやり、と言った感じの嫌なものだけれど。 「顔が赤いぞ」 誰のせいですか! 文句を言ってやりたいところだが、大きなしっぺ返しが返って来そうな気がして結局私は口を噤み、立花 先輩を睨みつけるだけにした。だが先輩に私の睨みつける攻撃は効いていないようで、一層笑みを深めただけだった。 にやにやといつまでも本を読み始めない先輩に苛立ち、指摘する。 「...本読まないんですか?」 「あぁ、本よりこっちの方が面白いからな」 こんな事になると知っていたのなら背もたれの仕事を甘んじて受けていたというのに! 逃げ場の無い立花先輩からの視線を受けながら、頬の熱が冷めるのを願いつつ私は唇を噛んだ。 ---------------------------------------------------------------------------↑戻る
潮江先輩と! 肩にそろばんを担ぎながら歩いている潮江先輩を見つけ、私はそそくさとその場から逃げた。 軽々とした様子でそろばんを担いでいたが、あれが十キロもあるということは日頃から使用している身としては、よーく 分かっている。普段からの訓練の賜物なのか先輩はそれを普通のそろばんのように扱う事が出来るようだが...か弱い私には肩に 担ぐなどもってのほかだ。まず肩まで持ち上げれるか分からないのだから。まぁ、私がどれだけ非力でか弱い女の子である かという話は置いておいて、こんな所をそろばんを持って先輩がうろついているという事は会計委員会の面々を集めに来た に違いない。それにはもちろん私も含まれていることだろう。今度は一体何日徹夜になることになるのだろう...そう考える と思わず私の足は潮江先輩から離れていったのだ。けれど、逃げたくなるのもしょうがないと思うのだ。会計委員は少し、 いや! ものすごく厳しいのだ。隈をこさえてまで委員会活動をしているのはうちだけだと思う。だから、逃げたくなって も...実際に逃げてしまってもしょうがないと思うのだ! というよりも勝手に足が動くのです。 一刻も早く潮江先輩から離れろ と。これって体が拒否してしまってると思うんです。精神的には罪の意識に駆られているのだけどね。今すぐそろばんを弾き 委員会のために...学園のために役に立ちたいと心では思っているんですけど。足が言う事を聞かないんですよ。これって もう、しょうがないじゃないですか。体は悲鳴を上げてるってことなんですもん。だから、だから、神様! 私は悪くないと 思いませんか! つらつらと潮江先輩から逃げてしまった事に対しての言い訳を並べていたのが悪かったのだろうか、それとも自分の行動を 正当化しようとしていたのが間違っていたのだろうか。いつの間にか行く手を阻むようにして潮江先輩が立っていた。 「どこに行くんだ」 「...え、あー、ちょっとそこまでです」 それでは私はこれで! 口早にそれだけを言い先輩の横を通ろうとしたが、がしりと肩を掴まれそれは叶わなかった。 そのままずるずると会計委員室に連れて行かれるのを振りほどきたい所だったが、痛いほどに力を入れて掴まれては逃げれる わけもなかった。 . . いつもの席に座らされ、机の上に一冊の帳簿が落とされた。それに視線を落としてから部屋の中に視線を這わせる。 あれ? 「潮江先輩」 「なんだ」 先輩はすでにいつもの定位置に座り墨を擦っていた。視線は手元に落とされている。 「他の子はまだ来てないんですか?」 そう、部屋の中には私と潮江先輩の二人だけだった。三木も左門も団蔵も佐吉も誰も居ない。不思議に思いながら先輩を 見つめると先輩は墨に落としていた視線をこちらに向けた。それから筆を手に持ち、墨の中に浸した。 「あぁ、今日はお前と俺だけだ」 今日はお前と俺だけ...? 一瞬、先輩が何を言ったのか分からなかった。ぱちぱちと瞬きを繰り返すと先輩がちらりと視線 を私に寄越してから意地悪く笑った。 「本当は三木ヱ門と俺でやる予定だったんだがな」 こと、と音をたてて筆を置き、正面から私を見て先輩は続けた。右の口角を吊り上げた笑い方はどうみても意地が悪いもの にしか見えない。私が打ちひしがれているのが楽しくてしょうがないとでも言いたげな顔だ。 「逃げたろ? 俺の姿見て」 「ギクッ!」 ギクッ! なんて言ってしまったら先輩の言葉を認めたも同然だ。だがだってまさか逃げていた所を目撃されていたなんて ! 冷や汗のようなものがじわじわと背中に出てきた。 「だからお前にした」 めったに見たことがない、満足気な笑みを浮かべ先輩はひどい事を言った。もっと他にその笑みを浮かべるのがふさわしい 時があると思うのだけど。 「...ひどい」 小さく呟いた言葉は潮江先輩にも向けられていたし、長々と何故私が逃げる事になったのか説明してあげた神様にも向けら れていた。 見逃してくれて三木ヱ門と二人でしてくれれば良かったのに...(これは潮江先輩に対して) 確かに心の中では役に立ちたいと思ってましたけど、体は拒否してるっていったじゃないですか!(これは神様に対して) .......などの様々な気持ちの混じった一言だったのだ。 「ひどいのはお前だろうが...人の顔見るなり逃げやがって...」 俯いていた顔を上げ、思わず潮江先輩を見つめる。そろばんを弾く先輩の指は相変わらず迷いがなく力強いものだった。だが、 肝心の先輩の表情は俯いていて分からない。声だけを聞けばいつもよりも覇気がないように聞こえ、まるで私が先輩を見て逃げた ことに対して傷付いているかのように私には聞こえてしまった。...勘違いかもしれないけど。そう考えると、先輩の姿を見て逃 げた事がすごく悪い事だったように思えて私は少し反省した。 あぁ、日頃からお世話になっている先輩の心を傷つけてしまうなんて...! なんて私は罪深いのだろう! 両手を握り、天井を仰ぎながら私の行為について悔い改める。 今度逃げる時は決して、決して、先輩に見つからずに逃げて見せます! 固く固く決意した時だ。 「さっさと計算を始めんか!」 潮江先輩の怒号が飛んだ。 ---------------------------------------------------------------------------↑戻る
七松先輩と! 「放課後、裏山に集合!」 次の授業を受けるために移動していた時だ。突然表れた七松先輩がそれだけを言って去っていった。 あまりにも突然の出来事に反応出来ずにいたが、少しするとそれが体育委員会の話だと理解でき、私は顔を歪めた。 なんでまた裏山に集合なのか? いつもであれば学園内で全員集合してから七松先輩の気分で、マラソンにするか、塹壕を掘るか、バレーにするかを 決めてから裏山なり中庭なりに行くというのに今日は裏山に集合らしい。少し授業が延びてしまったので、もう裏山 には体育委員会全員集合しているかもしれない。そう考えると自然と心が急かされた。 裏山に集合! なんてすごく適当な集合場所の告げ方だ。私が分からなかったらどうするんだろう。と、思いつつも 裏山にある少し開けた原っぱが集合場所だろうと瞬時に考えた私は推理力がすごいと思う。滝夜叉丸も同様にあの場所 が分かったかもしれないけれど金吾と四郎兵衛はどうだろうか。三之助はもし分かったとしても辿り着けただろうか...。 かわいい後輩達の心配をしながら歩いていると目的の場所にはあっという間に着いた。額にうっすらとかいた汗を手の平 で拭いながら前方に目を凝らしてみると、原っぱの真ん中に七松先輩が仁王立ちして待ち構えていた。 なんだかとても気合が入っているように見えて、私は帰りたくなった。だが、帰らせてくれるはずがない七松先輩は 私の姿を見つけると大きな声で呼びかけてきた。 「遅いぞ!」 「へぇ、すいやせん」 ぷんぷん怒る七松先輩にどこぞの下っ端のような口調で謝りつつも、原っぱに後輩達の姿がないことに首を傾げた。 腕を組んで私を待ち構えている七松先輩の下へ走って行くと先輩は満足そうに一つ頷いた。 「それじゃあ行くか!」 言葉と一緒に右腕を掴まれ、引っ張られる。突然の事に対応できずととと、と三歩足が進んだがそこで踏ん張って 立ち止まった。先を急ごうとしていた先輩は動かない私に不思議そうな表情をして振り返った。 「まだみんな来てません」 辺りを見回しても生い茂った草や背の高い木があるばかりで、人の気配が一つもしない。私がビリだと思っていたが どうやら、みんなこの場所が分からなかったらしい。と、なれば探しに行くか、ここで待つかしないといけないだろう。 どこに行くのか知らないが、置いて行ったりしたらかわいそうだ。いや、もしかしたら置いて行ったらいったで喜ぶ かもしれないが、そんなことは許さない。私たちは七松先輩という暴君を相手に一致団結、一蓮托生、死なば諸共 ...そう、つまる所運命共同体なわけだ。涙を流しつつ誓い合ったのだ。それなのに私一人が、七松先輩と地獄への マラソンだなんて......そんなことは許されない。絶対に! だが、私のそんな後輩を思っての発言(後輩達からしてみれば迷惑な発言)を聞いて七松先輩は首を傾げて、きょとんと した様子で私を見返すだけだった。これだけ見ると先輩はとても人畜無害に見える。 「今日呼んだのはお前だけだぞ?」 ...前言撤回、やはり人畜無害などではなかった。やはり七松先輩は七松先輩だったのだ。 無邪気な顔をして先輩は 私に恐るべき爆弾を投げつけた。その爆弾とはつまり、今日は私と七松先輩二人っきりで地獄へのマラソン。 「え、ええー、ふ、二人でマラソンですか...?」 私は半泣きだったかもしれない、だってそんな励ましあう仲間もいない中、七松先輩と二人でマラソンなんて...出来る 事なら今すぐに気を失いたい。気付いたら医務室の布団の中とかそういう展開を望む。 「いや、マラソンはしない」 必死に気絶したいと祈る私の願いが届いたのか先輩は私の予想を良い方に裏切ってくれた。なんだ、マラソンじゃなかった のか、とホッと息をつくが、待てよ...と思いつく。マラソンじゃないのなら... 「じゃ、じゃあ、バレーですか...?」 どうか先輩が首を振ってくれますように...と祈りながら目の前に居る七松先輩の顔を見つめる。 「いや、違う」 今度こそ私は緊張のために詰めていた息を盛大に吐き出した。あぁ、良かった。心の底から喜んだ。 「なんだ? マラソンやバレーがしたかったのか?」 ほんのり嬉しそうな顔をして尋ねる先輩に私は首がもげるのではないか、という勢いで首を振って否定した。 あまりに勢い良く頭を振ったものだから顔に髪の毛がばちばち当たって痛い。だが、その甲斐あって先輩には私の気持ちが 伝わったらしい。「そうかー、楽しいのになぁ」と、ちょっとだけ気落ちしたような声が聞こえた。 マラソンでもバレーでもないなら一体なぜ自分は裏山に呼び出されたのだろう。説明を求め、先輩を見つめるとまたしても 右腕を掴まれた。先輩の手は熱くて、皮がごつごつしている。 「よし、行くぞ!」 先輩の手の感触に気を取られている間に先輩は走り出した。慌てて私も転げないように足を動かす。 一体どこに行くのだろうか。目的の場所も教えてくれないままに森の中を駆けて行く背中を見つめながら私は、 けれど先輩が居るのだから大丈夫か、と考えた。先輩は確かに無茶な事をするし、私たちにもそれを要求するのだけれ ど、本当に危ない事になったら助けてくれるのだ。それは今までの事で十分すぎるほどに分かっている。 だから私たちは先輩の事をすごく頼っているし信頼している。そして、先輩も私たちの期待を裏切らない。 鬱蒼と木の茂った森の中は薄暗い。なので、前方に光りが溢れているのが見えて、開けた場所に辿り着いたのだと気付いた。 眩い光りに目が眩んで、私は目を閉じた。それなのに七松先輩は、いつのまにか走ることを止めた足をけれど大股で 光りの中に進んでいく。この人は眩しくないのだろうか。少しでも光りから逃れようと俯きながら、薄く目を開くと 七松先輩の迷い無く進む両足が見えた。その足が止まった。 「目を開けてみろ」 眩しさに目が慣れたのを感じつつ目を開くと、七松先輩の笑顔が目に飛び込んだ。それから掴まれたままの右腕を 引かれて崖のぎりぎりまで歩く。次に目に飛び込んだのは黄色一色の光景だった。眼下に広がるのはひまわりの群れだ。 「今日はこれを見せたかったんだ」 ひまわりのような笑みで七松先輩が笑った。 ---------------------------------------------------------------------------↑戻る
中在家先輩と! 現在の状況 中在家先輩と図書室に二人きり 何故、忙しい時はものすごく忙しいというのに暇な時はとことん暇なのだろうか。 貸し出して返ってきた本は全て元の場所に戻した。そして今は貸出しカードの整理をしている。すぐに終わってしまう 簡単な作業なので私一人で十分なのだけれど、中在家先輩も手伝ってくれている。 現在の状況をもっと詳しく話すなら、貸出しカードを入れてある小さな箱を挟んで中在家先輩と二人で背中を丸めて 、一枚一枚カードを確認している。 正直に言うと......気まずい。先輩のことは好きだし尊敬しているけれど、気まずいものは気まずい。 本当ならきり丸もここに居て三人で今日の当番をしているはずだったのだが、一年は組は授業で学園を出て行って まだ帰って来ていないらしい。だからと言ってきり丸の変わりに他の委員の面々である、怪士丸や久作や雷蔵を呼ぶ ほどではないだろう。と考えた中在家先輩と私は今日の当番は二人で行おうと決めたのだ。決めた、と言っても 中在家先輩に私が「別に二人で大丈夫そうですよね?」と言い、先輩がそれに一つ頷いただけだったけれど。 だが、私は二人で大丈夫ですよね? と、中在家先輩に尋ねた数刻前の自分に余計な事いいやがって! と怒鳴って やりたい気分だった。(私が言わなかったからと言って中在家先輩が他の面々を呼んでくれたのかは分からないが、 そこには目を瞑るとして) ここにきり丸が居たのなら、きっとアルバイトであった話だとか、は組であったちょっとした事件だとかを面白おかしく 話してくれて今のような気まずさを感じる事もなかったと思う。 ......そんなこと考えてもここにきり丸は居ないのだから意味の無い事だけど。 手に持ったカードの束から一枚抜き取り視線を落とすと、随分と延滞しているのが分かった。名前のところを確認 すると"潮江文次郎"の名前があったので、納得しつつそのカードを整理して纏めているところから弾く。また今度 、取立てに行かなくてはいけない。カードの束が随分と少なくなったのを感じながら、私は前方に座る中在家先輩 を盗み見た。黙々といつもどおりに無言で作業を続ける先輩に、私は急に焦りを感じた。それから、 何か話す事がなかっただろうかと頭の中の引き出しを開け閉めする。 きり丸がいないのだから、私が自分でこの空気を気まずくないものにする他ない。 そして一つ思い出した。いつかこんな日が来た時のためにと、取っておいた話があったのだ。 小さく息を吸い込んで言葉を探す。 「そ、ういえば...」 初っ端から緊張のあまり声がひっくり返った。恥ずかしさを押し殺して前方にいる中在家先輩の手を見ると、動き が止まっていた。どうやら私の話を聞いてくれる様子の先輩に、私は言葉を続けた。 「この間、先輩が読んでた本を真似して読んでみたんです」 手から視線を上げ、先輩の顔を見つめる。いつもの感情の読めない顔で先輩はじっと私を見ていた。 「そしたらすごくおもしろくて、先輩が読んだ本はきっと全部当たりだろうって思ったんです。それで続けて 先輩が読んでた本をもう一度借りてみたんです」 先輩はうんとも、すんとも言わない。いつもどおりだ。 「それじゃあ、すごく難しくて。読み終わるのに二週間かかっちゃいました!」 何で難しい本とか教科書を読んでると眠くなるんですかね? あははは.....。 ...失敗した。きちんとオチもつけたつもりだったのに先輩はくすりと笑うどころか、いつもの無表情である。 私の空しい空笑いだけが響く図書室に、誰か「馬鹿だなー!」と笑ってくれ! と願ったが、誰も居ないのに 笑ってくれるわけもない。 「ははは......はぁー。あっ、残り少しですね。カード、早く片付けちゃいましょうか!」 無理やりにこの話を終わらせて、私はまたカードに視線を落とした。...さっき以上に気まずいのは気のせいじゃない。 その時、微かに声が聞こえた。ぱっと顔を上げると、先輩が小さな声で話していた。疑問符を浮かべると、先輩の 口がもう一度動いた。反射的に耳を先輩の方に傾けて、神経を集中させる。 「... 」 呟かれた言葉は聞いたことがあるものだった。何だったっけ? と、首を捻ると思い出した。 先輩が紡いだ言葉は、私には難かしくて読み終わるのに二週間かかった本の題名だ。 「それです。読むのに二週間かかった本です」 続けて先輩が言葉を紡ぐ。つらつらと読み上げられるのは私が過去に借りた本の題名だった。 九つだろうか、読み上げられた過去に私が借りた本の題名を紡いでいた先輩の声が止んだ。何故、私が今まで借りた 本を知っているのかと訝しむと、先輩の視線が真っ直ぐに私を貫いた。 「......どれも読んだものだ」 先輩にとっては何気ない言葉だったのかもしれない。 だが、私にはその言葉は思わず動揺してしまう一言だった。 私が中在家先輩が読んだ後を辿っていたのが、知られたと思った。私と先輩とでは読解力に雲泥の差がある事に気付い たくせして、私は懲りずに先輩の後を辿っていた。 それは隠れるようにして行っていた秘密だ。 先ほど先輩に話したのはほんの一部の話だったのだ。そして話を聞いた先輩はきっと、私が先輩の真似をしたことに懲りて、その後は 先輩の真似をしていないだろうと考えたはずだ。だって私がそう取れるように話したのだし...。実際には私の貸出し カードには先輩のカードに書かれてある文字と同じものが連なっている。 恥ずかしくて顔が上げられない。何故、先輩は私が借りた本が分かったのだろう。顔が赤くなっているのを感じながら 視線を落とすと、先輩が私の貸出しカードを左手に持っているのが見えた。 気付いたら体が動いていた。飛び掛かるようにして先輩の手に抱きついて、先輩の手ごとカードを隠した。顔を上げる と先輩が珍しく、目を丸くして驚いた表情をしていた。私も驚いた。自分の行動にも、先輩の表情にも。 「ち、違うんです...! 決して、先輩の真似をしてたわけじゃ...!」 動転して必死に紡いだ私の言葉は、どう考えても"先輩の真似をしてました。"と言っているようなものだった。 やや経ってその事に気付いた私の顔にはますます熱が上ってくる。恥ずかしさのあまり体を丸めて、胸に抱いている ものにぎゅっと抱きつく。恥ずかしい。そればかりの感情に支配される。 すると、頭を撫でられた。優しい手つきに私はそっと顔を上げた。 「......とりあえず放してくれ」 少しばかり頬が赤い中在家先輩が自らの左腕を指差した。そこで、私は今まで抱きついていたのが中在家先輩の左腕 だったことに気付いた。 飛び上がり、後ろに下がった私は必死に頭を下げた。 ---------------------------------------------------------------------------↑戻る
食満先輩と! 食満先輩と食満先輩の部屋(善法寺先輩の部屋でもあるけど)に二人っきりという今の状況。 ついでに言うならば今は夜で食満先輩は寝巻き姿である。ゆらゆらと揺れる火がなんだかおかしな雰囲気をかもし出しているような気がしないでもない.....ってないない! 首を振って自らの言葉を否定すると目の前の食満先輩が心配そうに大丈夫か?と尋ねてきたので大丈夫です! と答えてかなづちを握った。本当はかなづちよりもゆらゆら揺れる火を握り消してしまいたかった。火傷になってもいい。 一体どこでどうなってこういう状況になったのかと言うと間違いなく数刻前のあの時だ。用具委員会の今日の最後の活動としてそこらじゅうにちらばった工具やごみなんかを片付けて、ようし帰ろう! と皆が食堂の方へと歩きだした中に食満先輩の姿が無い事に気付いた私は皆に先に行っといてと言ってから倉庫の方に引き返した。もしかしたらまだ仕事が残っていて食満先輩が一人で処理しようとしているのかもしれないと思ったからだ。時々、食満先輩がそうやって私たちの負担を減らしているのを知っている。けれど私としてはもっと頼って欲しいと考えている。だから、もし食満先輩がまた一人で仕事を終わらせようとしているのなら手伝おうと考えていた。思ったとおり倉庫の扉は開きっぱなしだった。 近づくにつれて中から工具がぶつかっている音が聞こえてくる。中を覗き込むと食満先輩が工具箱の中を開けて何かをしていると所だった。 「食満先輩」 「ん? あれ、さっき食堂に行ったんじゃなかったか?」 振り返った先輩は少し驚いたような顔をした。先輩の問いには答えになっていない「そうなんですけど」とかよく意味が分からない事を返して、構わずにそのまま倉庫の中に入って先輩の隣にしゃがみこむ。 「また仕事ですか? 手伝います」 「いや...仕事とはまた違うんだ」 「なにか壊れたのを修理するんじゃないんですか?」 「あぁ、いや...壊れたっちゃあ壊れたんだが、急ぎのもんじゃないからな」 「けど壊れたんでしょう?」 「まぁな...俺一人で大丈夫だ」 この話はこれで終わりだと言うようにせかせかと食満先輩は必要だと思われる工具を風呂敷の中に放り込んでいく。それを眺めながら私はムッとした。 歯切れ悪い物言いには、私を撒こうとしている食満先輩の思惑が見えている。 どうせまた一人で片付けようと思っているのだろう。私以外の子たちはまだ下級生で色々と心配なのは分かる。けれど私はもう五年生だし、下級生達と同じ括りにされてはかなわない。もっと頼って欲しいと思うのはわがままではなく責任感だ。 これでも一応用具委員なのだから。 「私も手伝います」 食満先輩が手に取ろうとしたかなづちを横から掻っ攫ってやった。先輩の手が目的を失ってだらりと下に垂れて、少し困ったような顔をした先輩と目が合った。 「俺らの部屋の物なんだ、だから...」 「学校の備品に変わりないです!」 学校の備品であれば用具委員が直す物であるはずだ。食満先輩を言い負かせた気で少し得意になって笑うと、先輩がしょうがないと言うように口角を上げながら頷いた。 「じゃあ頼むな」 「はい!」 私は張り切って頷いた。食満先輩に認められたみたいで嬉しかった。 かなづちを二本渡して善法寺先輩が夜保健室で番をするために今は部屋で仮眠を取っているので善法寺先輩が居なくなる夜に食満先輩の部屋に集合する事になった。 食満先輩が遅くなるから風呂に入ってから来いと言っていたのでその通り、私はお風呂に入ってから寝巻きで行くのもどうかと思って忍装束に袖を通した。まだ湿っている髪はめんどうなので下ろしたままに上機嫌で善法寺と食満と書かれた部屋にやってきたのだけれど...まず部屋の戸に大きな穴が開いていることに驚いた。それから続けて髪を下ろして白い寝巻き姿の食満先輩が出てきて驚いた。なんでか分からないけれど、ぐっと声が詰まってしまってジッと食満先輩を見つめてしまったけど先輩が不思議そうな顔をしたのでハッとして視線を引き剥がした。それから誤魔化すように口を開いた。 「ね、寝る準備万端ですね」 「おぅ、終わったらすぐ寝れる」 得意げな食満先輩がおかしくて私は思わず吹き出してしまった。 「すごいだろ、この穴。小平太の奴がバレーボールを投げ込んでな」 それがまた伊作に当たって大変だった。と食満先輩が少し遠い目をして言った。それに私は「ソっ、そうなんですか」とぎこちなく返した。何だか変だ。見慣れない食満先輩の姿や、二人っきりという状況に緊張しているかもしれない。 手元を見るフリをしながらちらっと食満先輩を見てみる。先輩は必要な分の木の長さがどんなものか測っている所だった。その姿はやっぱりいつも見慣れている“食満先輩”とは少し違う。中身はいつもと同じ食満先輩なのだ、それなのに何を変に意識しているのか! それに今考えるべきは戸の修繕についてだ。早く終わらせてこの部屋に戸を付けないと外から中が丸見えだ。それって考えるだけでもぞっとする。だって常に誰かに見られてるってことだろうし。くつろげる場所が無いってことだ。 つまり一刻も早く戸を修繕しないといけないということだ! 使命に燃える私は色々な雑念を頭から追い出して修繕に取り掛かった。 ぽつぽつと会話にも満たないような言葉を交わして私と食満先輩は夜通し戸の修繕を行った。 「へっくしゅ!」 沈黙は私のくしゃみによって終わった。風呂上りに髪が濡れたまま、うろうろしていたものだから体はすっかり冷えてしまったらしい。ぶるっと体が震える。 「大丈夫か?」 「大丈夫です!」 それまで手を動かしていた食満先輩が私のくしゃみの所為で手を止めてしまった。それに慌てつつ大丈夫だと答えるも先輩は手に持っていた鋸を放って行李の方に歩いて行った。鼻が垂れそうなので極力音をたてないように鼻を啜っていると一瞬風が吹き、頭に何かがふわりとかけられた。 何事かと頭にかけられたものを手で引っ張るとそれが何であるか分かった。濃い緑色のそれは食満先輩を探すときの目印みたいなものだ。 「それ羽織っとけ」 「...え!」 「言っとくがちゃんと洗ってるからな!」 「え、いや」 そういう意味の驚きではなかったのだけれど....。見当違いなことを少し慌てたように言う食満先輩に、私が意識しすぎなんだろうか...と考える。どういう意味でかどきどきする胸の前にそれを抱きながら私は食満先輩と交互に視線をいったりきたりさせてから頷いた。 「ありがとうございます...」 せっかくの食満先輩の好意だ、私はありがたく受け取ることにした。先輩が「あぁ」だとか答えているのを聞きながら私は立ち上がり、袖を通した。羽織るときにふわりと風が起こり、一瞬香ったのはきっと食満先輩の匂いだと気付いて無性に恥ずかしさを感じる。 「やっぱちょっと大きいな」 予想通り私が着てみると大きくぶかぶかで、文字通り服に着られている状態の私を見て食満先輩は少しおかしそうに笑みを浮かべながら感想を述べた。暖かくはなるだろうが見た目的に何だかまぬけなんだろうとは見ずとも予想出来る。 手出してみ。と言われるまま手を差し出すとぶかぶかで微妙に手が出ていた袖を食満先輩は私の手の長さに合わせて折ってくれた。 「さっきのぶかぶかなのもよかったが、これじゃ作業しづらいからな」 「...」 「...」 「...」 「へっ、変な意味じゃないからな?!」 「はっ、はい」 「ただ俺の服がでかくて、ちっちぇと思っただけで!」 「た、確かに食満先輩の服はでっかいです!」 「そうだ! 俺はでかくてお前はちっちゃい!」 「私は食満先輩に比べればちっちゃいです!」 「そういうことだ!」 「そういうことですね!」 何がそういうことなのかは自分で言っておいて分からない。ただ食満先輩の勢いに乗せられる形で同意の言葉を述べただけだ。 食満先輩はいつも以上に目を吊り上げて必死の様子なので先ほどの言葉はつい出てしまったのだろうと予想した。そこで先ほどの食満先輩から発せられた言葉を私は無意識にもう一度頭の中で繰り返してしまい、頬が熱くなるのを感じた。急激に顔に熱が上っていくのを感じ、それに伴い顔の色もきっと赤くなっていることを予想し、熱が上るのを止めようとしたがそんな器用なこと出来るわけもなく...だからと言って視線が合ったままの食満先輩から急に視線をそらすのはおかしいのでじっと見つめていると気のせいか食満先輩の顔まで赤くなっているように見えてきた。するとまたしても私の顔の熱が上がる。 「そ、それじゃあ修繕再開だ!」 「は、はいっ! 頑張りましょう!」 合ったままだった視線を強引にそらして食満先輩がやけに張り切った様子で腹の底から声を上げた。それに対抗して私も叫ぶようにして言った。 「おっ!その調子だっ!」 「はいっ!」 あきらかに先ほどまでとは違う空気に動きさえもぎこちなくなってしまう。その空気を変えたくて何か話題を探すものの今までどんな話を食満先輩と話していたのか忘れてしまった。まだ戸の修理は終わりそうにも無いのにこの妙な雰囲気のまま長い夜を過ごすのかと思うと...。食満先輩の様子を伺おうと手元は動かしながら視線だけを上げると、驚いた事に食満先輩と目が合ってしまった。あちらも驚いているが私も驚いた。またしても顔に熱が上りだしたのと、食満先輩の顔色が赤くなったのはほぼ同時だった。 だが次の瞬間食満先輩の顔色が赤から青に変色した。 私の背後を見ていることに気付き、私も慌てて後ろを振り返るとにやにやとした笑みを浮かべた立花先輩が立っていた。 いつから私たちのやり取り聞いていたのか...私も食満先輩同様顔が青くなるのを感じた。 青い顔色をした私たち二人の視線を受け、立花先輩はおやおやなんて言いながらその何か企んでそうな笑みを一層深める。 「夜中に何を騒いでいるのかと思い来てみれば...食満が用具委員の仕事にかこつけて後輩を部屋に連れ込んでいたのか」 「連れ込んでねぇ!!」 「連れ込まれてません!!」 ---------------------------------------------------------------------------↑戻る
善法寺先輩と! 「うわあっ!」 聞き覚えのありすぎる声が遠くから聞こえ、私はすぐにその場に直行した。後ろから友人の引き止める声「ちょっ、これ私一人で運べっていうの?!」が追いかけてきたが私は心の中で謝り(振り返る時間さえも惜しい)友人と手裏剣やらなんやらをたくさん詰め込んである箱を置いて振り返らずに全速力で走った。 現場にはすぐに到着した。 大きな穴がぽっかりと開いていてその周りにはトイぺが散らばっている。これは間違いない...事件はここで起こっている...! 駆け足で近寄り(その際、仕掛けられている穴を避けながら)中を覗き込んでみると予想通り、中には伊作先輩が居た。泥を被ってぼろぼろの状態の伊作先輩は今まさに助けを呼ぼうとしていたところらしく、口を大きく開けているところだった。 「伊作先輩!大丈夫ですか?!」 綾部は迷惑な事にいつもより張り切ったのか、穴はすごく深くて伊作先輩が随分遠くにいるように見える。私が突然顔を出したので伊作先輩は最初驚いたようだったけれど、このやり取りは既に何度か繰り返しているのですぐに気を取り直したようにその表情が驚きから苦笑に変化した。頭の後ろを右手で掻いて、少し恥ずかしそうだ。 伊作先輩は私がこうやって穴の中に先輩を見つけた時、いつもその仕草をする。 「大丈夫、慣れてるから。それで、悪いんだけ...」 「分かってます」 皆まで言わなくても分かっていますとも。と、私は右手を顔の前にかざして首を振った。これも既に何度か繰り返しているやり取りだ。この後、伊作先輩は眉尻を垂らしてお礼を言うのだ。そしてそんな私の予想通りに伊作先輩は「ありがとう」と言った。私はその言葉に俄然やる気が出て、懐から常に携帯している縄を取り出し、それを体に巻きつけてから穴の中の伊作先輩向けて垂らした。 本当は木とかちょっとやそっとじゃ動きそうに無い物に巻きつけた方がいいのは分かっているのだけど、生憎と周りには縄を巻きつけられるものが無かった。 私の力で引き上げるしかなさそうだ。 私一人の力で引き上げるのは今回が初めてだ。大丈夫だろうか、と一抹の不安を感じながらも私は綾部にこんなとこに穴掘りやがって! と悪態をついて、頭の中ではこの戦いが終わったらもう少し長い縄を携帯するようにしようと考えていた。それなら、どこかに巻きつけることが出来るはずだ。 私は深呼吸をしてからじりじりと後退して、大声で穴の中に居る伊作先輩に話しかけた。 「引っ張りますよー!」 「悪いけど、頼むよー」 「まかせてください!」 伊作先輩に頼られたのだ、条件が悪かろうが、腹を縄で締め付けられること必須だろうが頑張るしかない。 縄を両手で握って私は後ろに全体重をかけた。伊作先輩の全体重が私の手とお腹にかかっている。ぎりぎりと締め付けられるお腹は私が考えていたよりも痛かった。 「し、しまるっ!!」 けれど私の手に伊作先輩の命が掛かっているのだ、手放すわけにはいかない!! 気合いを入れた私は少しずつだけれど後退することに成功した。つまりはほんの少しずつ伊作先輩を地上に近づけることが出来ている。 よし、このまま一気に! という気持ちとは裏腹に徐々に足が動かなくなり、それどころか逆に体が穴に向かって引きずられ始めた。お腹はぎりぎりと締め付けられるし、手の平は縄で擦られるし...ちょっとこれはやばくないか? 「だっ、だれか」 まかせてください! なんて大口を叩いたくせに私はついに根を上げて声を絞り出した。何だか限界までお腹が締め付けられて何かが口から出そうだ。どうやら気配で何かを察したのか、穴の中から大丈夫かと私に尋ねる伊作先輩の声が聞こえたが、私は答えることが出来なかった。自分の顔色は今とんでもないことになってそうだ。 「大丈夫か」 背後から声が聞こえたと思うと手が伸びてきて、縄を握った。その瞬間締め付けられていたお腹の力が緩まる。 滞っていた体の中の血がようやく全身に巡っているような妙な感覚を味わいながら手に力を入れて私も縄を引っ張った。 「ありがとう。助かったよ二人とも」 泥だらけの伊作先輩がにこにこしながらお礼を言ってくれる。それだけで私は口から何かが出そうなほどお腹を締め上げられたことなんてコロッと忘れてしまった。怪我をしている様子ならこのまま医務室に着いて行って手当てをしようかと思ったものの、泥だらけなだけで怪我はしていないらしい。医務室の当番は今日は数馬しかいないということでもう一度お礼を言ってから伊作先輩は足早に駆けていってしまった。 一仕事終えた私の胸には充足感が満ちている。今日の行いもきっと無駄にはならないだろう。ちりも積もれば山となるって言うし。 私は縄を懐に仕舞いながら隣に立つ、私のお腹の恩人に頭を下げた。 「立花先輩ありがとうございました。おかげで口から色んなものが出ずにすみました」 「確かにひどい顔をしていたからな」 「...立花先輩って意外にいい人なんですね」 「ほぅ...助けてやったというのに随分となめた口を利くではないか」 「いひゃいひゃい!!」 「礼は、そうだな。私の質問に正直に答えるだけで許しておいてやろう」 「えっ! お礼取るんですか?!」 吃驚した私に立花先輩は伊作先輩の笑顔とは程遠いにやりとした笑顔を浮かべた。 . . . 昼下がりの医務室にて 「お前の後輩に自虐的な趣味を持っているのがいるだろう」 「...え? 誰のこと? っていうか、そんな趣味の後輩いないよ」 「居るだろう。腹に縄を巻きつけて自らを締め上げて喜んでいたあの娘だ」 「それは僕を助けようとしてくれたからで決してそういう趣味なわけじゃないよ!」 「まぁいい。先日聞いた話なんだが」 「うん?」 「何故いつも伊作が穴に落ちるとすぐに現れるのか聞いたんだ。お前は知っているか?」 「いや、いつも助けを呼ぶ前に助けに来てくれるから不思議だったんだよ」 「それで聞いてみたんだ。別に半日くらい放っておいても伊作は大丈夫だぞ、と」 「...放っとかないでよ」 「するとだな、大丈夫かもしれないがそうなると計画が無駄になると言うではないか」 「...計画?」 「あぁ、どのような計画かと言うとだな」 「うん...」 「弱っている隙に付け込む計画らしい」 「...は?」 「つまりだ、伊作が心細く穴の中に居るのを助けて己に惚れさすという計画らしい」 「......は?!」 「あざといと思わんか」 「...いや、え...?」 「それだからいつも伊作が穴に落ちると真っ先に駆けつけるらしい。手柄を誰かに横取りされんためにな。」 「うん...うん?」 「顔が赤いぞ、どうした伊作」 「...え、そう?」 「そういえば、このことは誰にも言うなと言われていたのだ。ここだけの秘密にしておいてくれ」 「...僕に言ったらお終いじゃないの?」 「あぁ、だが私は意外にいい人らしいからな」 「......なにそれ?」 ---------------------------------------------------------------------------↑戻る
左門と! 今日の放課後はのんびり日向ぼっこの予定だったのが急遽変更になり、不本意ながら委員会活動になってしまった。 何やら帳簿の提出期限が変更になって、急いで完成させなければならないらしい。 今日は間違いなく徹夜になるだろうな。と思いながら頭に浮かぶのは潮江先輩の濃い隈だ。 女の子なのにあんな悲惨な隈は出来るなら作りたくない。睡眠はとても重要なものなのだ。 それなのにうちの委員会――会計委員会はそんなことおかまいなしに、夜どころか朝まで委員会が続くことなど ザラにあるのだ。悲しい事に......。 ここまで聞いたなら憂鬱な気分になるのも納得がいき最悪な委員会だと思われるかもしれないが、うれしい事もある。 かわいい後輩の存在だ。 みんな私に懐いてくれているかわいい後輩達だ。(え? 先輩? 先輩はまぁまぁ...置いといて) 一年の佐吉と団蔵はもちろん、三木もかわいいかわいい後輩達だ。だが、その中でも一番かわいいのは...いや、 先輩としてはそんな一人だけ贔屓するだなんてそんなことはあってはならないことだ。とてもじゃないが、このことは 大きな声では言えない。だけど、私は思うのだ。左門がかわいすぎるのがいけないのだと! 私は断固として悪くない...! あの私を見つけた時の心底嬉しそうな顔に、あのでっかい口に、感情を体全部を使って表してくるところだとか。 何より一番かわいいのは頭を撫でてやった時の表情だ。 そっくりなのだ...。 あぁ、左門のことを考えていると頭をよしよししてやりたくて手が疼いてきた。 これは早いとこ委員会に行って左門を撫でなくてはいけない。 ゆっくりと動かしていた足を少し小走りにして先を急いでいると、ちょうどいいところに前に見覚えのある萌黄色の 装束を着た三人組を見つけた。 「さもーん!!」 大きく声を上げて手をぶんぶん振る。すると三人の中の一番小さいのがパッとこちらを振り返った。 遅れて残りの二人もこちらを振り返ったのが目の端で見えた。 「先輩っ!!」 嬉しそうに満面の笑みを浮かべる左門は全身で感情を表している。なんてかわいいんだ! 私も自然と笑顔になって手を広げる。すると左門は嬉しそうに走り出した。だが、何故か微妙に向かう方向を間違っている。 まぁ、これもいつものことだ。左門の方向音痴なところに慣れっこな私は左門の向かっている軌道に先回りして、 手を広げていつでも左門が飛び込んで来れるように準備万端で待機した。 「左門っ!」 「先輩っ!」 がしっ! 無事に腕の中に飛び込んできた左門の頭をがしがしと撫でてやる。 「えらいぞー左門!」 「先輩痛いですっ!」 「ごめんっ!」 「大丈夫ですっ!」 にぱっと笑顔の左門に今度は手加減して頭を撫でた。目を細めて左門は嬉しそうだ。そうだ、この表情だ...。 本当にそっくりだ...。私には左門にしっぽがあるのが見える。 こんなこととても誰にも言えないが、左門はうちで買っている犬にそっくりなのだ。どうやら私は、左門と愛犬の姿をだぶらせているようなのだ。 そんなこともあって私は左門がかわいくて仕方がない。 「よぉーし! じゃあ委員会に行こうか!」 「はいっ!」 元気よく返事をしてくれた左門の右手を取ると、ぎゅっと小さい左門の手が握り返してくる。 「富松くんと次屋くんにはちゃんと言った?」 「あっ! ...さくべー! さんのすけー! 委員会に行ってくるー!!」 大きな声で事後報告する左門に富松くんと次屋くんは、おぅ! とか、行って来い! だとか言った。その二人に手を振りつつ 私と左門は委員会に向かった。 「左門! 私のこと好き?」 「大好きですっ!」 「私も大好きじゃーこのやろぉっ!(がしがし)」 「先輩痛いですっ!」 「ごめんっ!」 . . . ☆ がしがし頭を撫でられている神崎くんを見ての富松くんと次屋くんの感想 「あれさぁ...」 「言うな。三之助...」 「絶対さぁ...」 「言うんじゃねぇ! 三之助...!」 「好きの意味違うだろ」 「おぉぉぉ...! 言うなっつったのに! おめぇ...!」 「だってどう見ても...」 「皆まで言うんじゃねぇっ! 左門の好きと先輩の好きは全然意味が違うとかそんなことぜってぇ言うんじゃねぇぞ!」 「いや、作兵衛が言ってるし」 ---------------------------------------------------------------------------↑戻る
三之助と! 「悲しいお知らせです... 」 「いやだやめて聞きたくない!」 滝夜叉丸曰く悲しいお知らせを聞くことを拒否したというのに、それに構うことなく滝夜叉丸は無慈悲にも疲れた表情 を浮かべて口を開いた。 「三之助が行方不明になりました... 」 「もぉー... 聞きたくないって言ってるじゃんかよぉ...」 げっそりと言葉を吐き出すと、滝夜叉丸も肩を落としてげっそりした。きっと、隣にいる四郎兵衛と金吾もげっそり していることだろう。それとも既に意識が飛んでいて聞こえていないだろうか。 山を越え谷を越え...山を越え谷を越え...を永遠に繰り返しているような心地で地獄のマラソンもそろそろ終わりに 近づいた頃だろうか、と赤い夕陽を見て考えていた時だった。先を行っていた滝夜叉丸が疲れきった表情で戻って 来たのを視界に捕らえたとき、既に私はこの後の展開が見えていた。それでも、少しの希望に懸けていたというのに... 希望はあっけなくも粉々に打ち砕かれた。三之助が行方不明という言葉でもって...。 無自覚方向音痴の三之助は目を離せばすぐに見当違いな方向へ走り出してしまう。なので、今日は滝夜叉丸がその 方向音痴が迷子にならないように見張っているはずだったのだ。 「それがどうしてこうなったんだよぉ...!」 「す、すいません。三之助の奴、途中で足を滑らせて落ちていったんです。それで助けに行こうと思い、そこから 動くなと言ったのですが...大丈夫だと言って歩き出してしまい...」 「行方不明、と」 「... はい」 「...」 「...」 「なんでだよぉぉぉぉぉ!」 「すいません ...!」 「いや、滝夜叉丸は悪くないよ... 悪いけど」 「... はい(どっちなんだ)」 「... っていうか落ちたのに怪我しなかったの?」 「はい。ぴんぴんしてました」 「不死身か、あいつ...」 怪我をしなくて良かったと本来であれば言う所なのだろうけれど、下手に怪我をしなかったから歩き回ってしま ったのなら三之助を恨めしく思う。はぁ、とため息を吐き出すと滝夜叉丸がもう一度申し訳なさそうに謝罪を口に した。いつもは元気に跳ねている横の髪の毛もへちゃりと元気がなく、泥だらけの姿に私は眉を下げた。 それからほぼ同じ目線にある滝夜叉丸の頭に手を置いて、ぽんぽんと叩く。先輩の癖に後輩を責めてばかりいた先ほど までの自分の発言を後悔しながら。 「滝夜叉丸、七松先輩にこのこと伝えてきてもらっていい?」 「はい!」 勢いよく滝夜叉丸が頷いたのを確認してから隣に居る、四郎兵衛と金吾を見遣る。すると、二人ともとっくに意識が ないかと思っていたのにばっちり目を開いてこちらを見ていた。 「四郎兵衛と金吾も手伝ってもらっていい?」 「「もちろんです」」 二人は力強く頷いて快く返答してくれた。その姿が頼もしい。 こうして三之助捜索隊が出来上がったわけだが、三人一緒で行動するのでは効率が悪いと思い四郎兵衛と金吾は二人 で行動するように言い置いてから一人山の中を彷徨っている。 滝夜叉丸が最後に三之助を見かけたというところまでやってきたのだが、当然だがすでに探している姿はなかった。 きっといつものように学園とは見当違いな道を歩いていったのだろう。 そして、その見当違いな道を推理するのはとてもじゃないが無理だ。 どうするか、右か左か... はたまた前か後ろか。上と下というのは無いと思うが...。 暫く考えてみるが結論はもちろん出なかった。なので、自分の直感を信じる事にする。私は右足を前向けて踏み出した。 「いないなぁ...」 赤い夕陽はすでにその身を半分以上隠してしまっている。あと少し、あと少しで夜がやってきてしまう。 日が沈むまでには見つけたかったのだが、無理だろうなと小さく諦めの息をつく。暗くなる前に四郎兵衛と金吾だけ でも学園に返した方がいいかなぁ。と思いつつ地面に落ちている葉っぱを蹴りながら歩く。 「あーあー、さんのすけ〜」 こんなこと言って出てきたなら苦労しないのだが、と思いながらも何か大声を出してこの鬱憤をはらしたいと思った 私はどうせ叫ぶなら三之助の名を呼んだ方がいいだろうと腹の中にたまったものを吐き出す。 「でておいで〜」 大きく足を振り上げると茶色の落ち葉がたくさん上に舞い上がった。そしてゆっくりとまた地面の上に落ちていく。 その様子をじっと眺める。 「呼びました?」 「ぎゃあぁぁぁぁ!!」 誰もいないはずのすぐ後ろで声が聞こえ、私は大声を上げて飛び上がった。急いで首を捻り振り向くと、なんだか間抜け な顔をした三之助がいた。 ... ... え? ... 三之助がいた... ? 「... うわぁぁぁ!! 三之助!!」 「わ、なんすか」 突然叫んだ私に三之助は驚いて少しうろたえて表情を歪ませる。あきらかに変な奴に会ってしまったという感じだ。 その失礼すぎる表情に私の頭は一気に冷めた。 「なんだそのおかしな奴を見る目は! え?」 「なんなんスか。絡まないでくださいよ」 心底迷惑そうな顔をする三之助に迷惑をかけているのは現在進行形でお前だ! と怒鳴ってやりたい気持ちをごくん と飲み込んだ。そしてそれの変わりに出てきたのは安堵のため息だった。 「ため息つくと幸せが逃げるらしいですよ」 「誰のせいだっ!」 飄々といつもの表情を崩さずに言う三之助にムカッときた私は噛み付くようにして三之助に言い返した。それに対して 三之助は驚いたように二度瞬きをして意外そうな顔をする。 「え、俺?」 「俺だよ。俺以外にいねぇだろ。」 「先輩、口悪いっスね。そんなんじゃ後々困った事になりますよ」 「なんも困んねぇよ」 「困りますよ。嫁の貰い手がいないとかで」 「うるせぇっ!!」 さっきまでの三之助をやっと見つけたという安堵していた気持ちなど消えてしまい、今私の中に沸々と湧いている感情は 怒りだ。生意気で口の達者な後輩に疲労も合わさって爆発しそうだ。それを爆発させないように自分の中で沈静さ せようと私は大きく息を吸い込んだ。 吸ってー吐いてー吸ってー吐いてー 「よし、帰ろう!」 「今のなんなんスか? 生まれそうなんですか?」 「生まれるか! ばか!」 見当違いなことを冗談なのか真面目に言ってるのか判断のつかない表情をして尋ねてくる三之助を無視して、手を延ばし た。延ばした先には三之助の左手がある。また迷子になられては敵わないので手を握って学園まで帰ろうと思うのだ。 普段、三之助を探し出している富松くんは捕獲した後、それでもあっちこっちに行こうとする三之助を縄で巻きつけて 学園まで連れ帰っているが私は生憎と縄を持ち合わせていなかった(持っていたら持っていたで怖いが)なので手を繋ぐ事にしたのだ。 三之助の手は少しひんやりとしていて大きい。さぁ、帰ろう。と、手を引っ張ってそのまま歩こうとしたのが、三之助が動かないので つんのめってしまった。なんだ? と後ろを振り返ると、三之助がまじまじと繋がれた手を見ていた。 なにかおかしなところでもあったのだろうか? 「先輩は...」 「?」 未だに繋がれたままのそこから視線を外さずに三之助が呟いた。一体どうしたというのだろう。私は耳を澄ました。 「甘えんぼですか?」 「... え?」 至って真面目な表情で三之助が私の目を見ながら言う。それから顎で繋いだ私たちの手を指す。 「だって、手」 「いや、手繋いでるけど別に繋ぎたくて繋いでるわけじゃないから」 「甘えんぼの上に照れやなんスか?」 「違うよ! なんでそうなんの?! あんたがどっか行かないように手繋いでんの! 本当は縄の方がいいけどさ」 「... え? 先輩、俺のこと縄で縛りたいんスか?」 「違わい! 人を変態みたいに言うな!」 「え、けど今...」 「富松くんはいつも縄で三之助をぐるぐる巻きにしてるから!」 「...あぁ」 納得したように相槌を打つ三之助はやっと歩く気になったらしい。 早く学園に帰りたい私はとりあえず、四郎兵衛と金吾 が三之助を探している辺りに向かって歩く事にした。三之助は大人しく私に手を引かれながら歩いている。 「作兵衛はアレ、趣味ですよ」 「... え?」 「作兵衛は俺と左門を縛るのが趣味なんス」 「...... え?」 思わず歩みを止めて振り返った。 すると三之助はやっぱり冗談を言っているような顔をしておらずに私を見返してきた。 「え? いやいや、冗談もほどほどに...」 「冗談じゃないですよ」 「いやいや...」 「この目を見てくださいよ。嘘なんてついてない目でしょ」 目を見ろと右手で自分の右目を指すので、私もついついその指の動きに従って三之助の目を見た。 見てみろと言われ見てみたが、それで嘘を言っているのか真実を言っているのかと問われても分からない。 三之助の眠そうな目を覗き込むと一歩、三之助が足を進めてきた。 首を傾げつつ依然、三之助の目を覗き込む。 また、三之助が一歩近づいてきた。 「三之助」 「なんスか」 「いや、近いんだけど」 「先輩がよく見えるようにという俺の思いやりです」 「あ、そうなんだ。ありがとう」 「どういたしまして」 そう言うとまたしても三之助は足を進める。 私への思いやりだとしても、近すぎる距離に私が後ろに一歩下がると手を引っ張られた。私が主導権を握って繋いで いたはずの手がいつのまにか三之助に主導権を奪われている。それを証拠に私は手を放しているというのに三之助 に掴まれている為に手が放れない。そのことに戸惑いつつ目の前の三之助に抗議する。 「ち、近いから」 「そうっスか?」 背中を逸らせて三之助から距離を取ろうとしたのだが、何故か三之助が私の目を覗き込むようにして近寄ってくるので 全然逃げれていない。 このままでは私の背骨が悲鳴を上げる... ! 「ちょっ、近いって!」 「先輩って...」 三之助はどうやら私の話を少しも聞いていないらしい。それともわざと聞こえないふりをしているのか。 どちらにしても私の言葉を綺麗に無視だ。...私一応先輩なんだけど。 背中が曲がりすぎてこのままじゃ後ろに頭から倒れこんでしまいそうだ。顔が引き攣っているのが見えているだろうに 三之助はお構いなしだ。 「かわいいですね」 「...はぁ?」 「いや、先輩ってかわいいですね」 「...はぁ?!」 「だから、先輩って...」 「もういいから! ちょっとお前黙れ!」 思いがけない三之助の言葉に頭がこんがらがっていると三之助がやっと離れてくれた。だけど依然手は放してくれない。 本当は手を振り解いてきっと赤いだろう顔を隠すために茂みにでも身を隠したいが、そうするとやっと見つけた三之助 がまたどこかに行ってしまうかもしれない。ようやく見つけたというのにその展開は勘弁して欲しい。なので手を放せない。 身を隠せないならせめてもと思い、三之助から見えないように顔を背けながら先を急ぐ。 「先輩やっぱり照れやなんスね」 「...もう頼むから喋るな...」 「なんでそんな疲れてるんですか」 「お前のせいだよ!」 「え、俺?」 「俺だよ。俺!」 「っていうか先輩、耳まっかっスよ」 「うるさい! もうやだこいつ...」 何故か今日に限って見当違いな方向に走って行こうとしない三之助は大人しく私の手を握ったまま後ろを歩いてくる。 がさがさと落ち葉を踏みしめながら私は色んなことを知ってしまった。 三之助の手が私よりも大きいとか。どきどきうるさい心臓の音とか。いつまでも引かない顔の熱だとか。 あぁ、それから富松くんのあんまり知りたくなかった趣味だとか。 ---------------------------------------------------------------------------↑戻る
拍手のお礼でした。先輩後輩がテーマになってます。 |