|
玄関ホールで、体育館で、中庭で、人がたくさん居る所に行くとつい僕の目は見知った後姿を探しだす。 最初は無意識だった。特に何かを考えて人込みの中に視線を漂わせていたわけじゃない。 気付いたのは三郎が誰を探しているのかと問いかけてきたからだ。僕はそれまで何故人込みに視線をやっていたのか 分からなかったので「なんとなく見てただけだよ」それだけ返した。自分が誰かを探しているなんて思ってもみなかった。 だけどそれが違うことに気付いたのは人込みの中、皆が同じ制服を身に纏っているのに彼女をすぐに見つけ出せる ことに気付いたから。その時、唐突にあの時の三郎の言葉に返すべき言葉が浮かんだ。 「さんを探してたんだ」 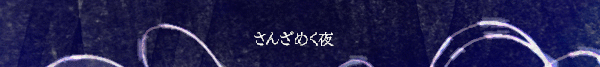
彼女とは去年同じクラスだった。だからと言って親しい友達というわけではない。クラスメイト 彼女についての印象は、大人しそうな子、それだけだった。 そんな関係に少し変化が起きたのは、この教室での授業も残すところわずかという時だった。学年末テストという 一年のうち最も大きな、そして最後のテストも終われば後はのんびりと時間を過ごすことが出来る。その時はその大きなテストも 終わり、春休みを前にした少しふわふわした空気が漂っていた時だったと思う。何でその日、僕は一人で教室に居たのか 今となっては思い出せないのだけど...僕はその日、放課後の教室に一人で居た。 多分後で三郎やハチや兵助や勘右衛門とも合流したのだと思うのだけど、そのとき僕は人気がすっかり無くなった教室 で窓枠に肘を乗せて外を眺めていた。グラウンドには野球部が練習に精を出していて、それを眺めて僕は時間を潰していた。 下校時間がとっくに過ぎた時間ということもあって校舎の中はひどく静かだった。冬独特の匂いが鼻先をかすめる 所為で少しだけ寂しさを感じたのをよく覚えている。きっと空気がそうさせたのだと思う。僕は普段そんなに繊細じゃない。 胸をかすめた寂しさを誤魔化そうと背筋を伸ばしたときだった。不意に耳が拾い上げたのは微かな声だった。 その音の正体を見極めようと耳を澄ましてみれば、踵を床に擦るような音と共に聞き覚えのある音楽を口ずさんでいる らしい声が廊下から聞こえてきた。微かで、きっと今日みたいに静かじゃないとその声に気付くことは無かったと思う。 それほどに声は控えめに廊下に響いていた。 微かに聞こえる声は冬の空気のように澄んでいて、だけどさっき感じた冬の寂しい印象は感じなかった。 ただ楽しそうなことがその声と、足音から伝わってくる。まるでステップを踏んでいるように聞こえる足音は不規則な リズムでその音を刻む。それだけでもその人が今とても機嫌がいいことが伺い知れた。 でたらめなリズムで聞こえる足音に僕は思わず口元が綻んだ。それとともにその澄んだ声の持ち主に興味が湧いた。 廊下を覗いてみたい。そんな衝動に足が動いてしまいそうになる。けれどそれをしてしまえばこの歌は止んで、 でたらめなステップも止まってしまうことは容易に想像がついた。それならばここに居て、ひっそりと聞き耳をたてていたい。 だけどその僕の望みは意外な形で潰れてしまった。少しずつ近づいてくる声に、てっきり曇りガラス越しに人影が通過して行く姿を見ることになると思っていた 僕の予想は外れて、教室のドアが開いた。 そこに見つけた意外な人の姿に僕は目を丸くした。だが、僕がそうやって衝撃を 受けている間も歌は止まずに、その澄んだ声の持ち主は視線を自らの足に向けていて教室の中に居る僕に気付いていない様子だった。 声をかけるべきか迷っていると、ようやく異変に気付いた様子で顔が上げられる。ちょうど正面に居た僕は音が聞こえそうなほどしっかり目があってしまった。 細い肩が跳ねて、肩にかかっていた長い髪が揺れる。次いで目が見開かれ、顔が徐々に赤くなっていくのを僕は居心地悪く控えめに見つめた。 やがて耳まで真っ赤になったさんは俯いてしまった。 髪の間から覗く耳を隠すかのように左手で真っ赤な耳朶を触っている。 「......誰も居ないかと思ってた」 「実は居たんだ。......忘れ物?」 さっき聞いた微かな歌声よりも更に小さな呟きに、僕は出来るだけ軽く返した。それからさり気無く話題を変えた。 もう少し仲が良かったのなら「何かいいことあったの?」と、からかい交じりに聞けるのだけれど僕とさんは仲が良い、 悪いの前の関係だ。今まで交わらなかった線が今日初めて交差する、そんな感じだ。 「うん。ちょっと」 話題が変わったことに見るからにホッとした様子でさんは耳から手を離して、自分の席へと歩いていく。 ちらりと見えた耳はまだ少し赤さを残している。さんの席は窓際から二番目の列で、前から数えるよりも後ろから 数えた方が早い位置だった。ともすれば僕がいま立っている窓際の列の最後尾の後ろのスペースからは比較的近い位置だ。 椅子を引いて、しゃがんで机の中を覗き込んでいる姿を眺めながら僕はさっきの澄んだ歌声の持ち主が彼女であると まだ信じられずに居た。よく考えてみれば僕は彼女の声をちゃんと聞いたことが無かった。 「さっきの歌...」 「あっ、うん!」 驚かすつもりは無かったのだけれど、さんは飛び上がってこちらを振り返った。長い髪が揺れて空中に舞う。 振り返った顔はやっぱり赤く染まっていて、口元は緊張したように真一文字になっている。恥ずかしがっているのは その表情を見れば一目瞭然だった。笑いたいところを我慢しながら、やっぱりさっきの歌声はさんだったのだと確信した。 そうするとおのずとでたらめなステップを踏んでいたのも彼女だという結論が出た。 「僕もあの歌好きなんだ」 大々的にCMで流れてはいないけどそんなにマイナーと言うわけでもない。そこそこ名の知れたバンドで、僕もCDを数枚持っている。 だからちょっとした共通点を見つけた気でそう言った。 「そうなんだ!」 さんが弾んだ声で嬉しそうに言う。さっきまで緊張していた様子だった口元は綻んで、目は気のせいでなければ 輝いているように見えた。僕はちょっとした会話のつもりでの言葉だったので、想像以上の食いつきにちょっとだけ驚いた。 そんな僕を見た途端、さんはちょっと困ったように眉尻を下げて笑った。自分を恥じているように綻んだはずの口元はきつく結ばれる。 「好きなの? あのバンド」 僕は慌てて今にも切れそうな糸を繋ぎ止める様にして言葉を繰り出した。 「うん。けど友達で好きだって子がいないから......」 だからさっきの反応だったのだ。仲間を見つけたさんは嬉しかったのだろう。 さっきの反応とは違ってさんの声は冷静で淡々としている。 熱せられた石に冷水を浴びせたみたいに変わった反応に僕は先ほどの自分の反応を後悔した。 「あった」小さい声は僕に向けてのものじゃない。どうやら忘れ物を彼女は見つけ出したらしい。 立ち上がってスカートの裾を手で払うとちょうど入ってきた西日の中でほこりがきらきら舞っているのが見えた。 出て行く雰囲気を漂わせるさんに「忘れ物あったの?」なんて、答えの分かりきっていることを尋ねた。 「うん」頷いたさんは椅子を元通り机の中にしまった。ガガガ、椅子と床が擦れる音が響く。 「不破くんも好きって聞いてびっくりしたよ」 “不破くん”覚えてたんだ。ほぼ一年同じ教室に在籍していたというのにさんに名前を呼ばれたのは初めてな気がする。 それとも呼ばれたことがあったかもしれないけれど、僕が意識してなかったから記憶に残っていないのかもしれない。 だけど今日のそれは深く頭に響いてくるようだった。 「あんまり有名じゃないし」さんはそう付け加えるとゆるく笑みを浮かべて、そのままドアに向かって歩いていく。 「僕もびっくりした」 どちらに対しての言葉なのか自分でもわからないまま背中に向かって声を掛けると、長い髪が揺れてさんが振り返った。その手はもうドアの取っ手に触れている。 「うん」微かな呟きが聞こえたと思うとドアが開いた。 「じゃ、ばいばい」 「うん。ばいばい」 ドアが閉められると教室の中にはまた僕一人だけになった。廊下からは歌も、ステップも聞こえてかなかった。 変わりに走る足音が聞こえたかと思うとそれもだんだんと遠ざかって聞こえなくなった。 カキン、小気味良い音がグランドから聞こえる。けれど僕は振り返らなかった。今起きたことについて考えるのに忙しかった。 胸の中に確かに存在した寂しさはいつの間にか消えていた。 進級した新しい教室の中には長い髪を下ろした背中は無かった。 . . . 自分が誰を探していたのか自覚はしたけれど、それで何かが変わるわけじゃなかった。さんとは相変わらず 話をする機会は無かった。同じクラスであればまた違う展開があったのかもしれないけれど、違うクラスであれば ほぼ共通点は無いに等しい。 朝の通学路は人で溢れている。 たくさんの人が歩いて学校に向かう中に目を引く後姿を見つけた僕は無意識に焦点をその背中に向けた。 もしかして...そう思うけれど、致命的なほど髪の長さが違う。背中まであるはずの髪が肩のあたりで揺れているのを見て、 僕はやっぱり人違いだと結論を出した。彼女を見分ける方法として髪の長さで判断していたところもあるのに、 何で今日は間違ったのだろう。自分で自分を不思議に思いながらも依然その背中から視線を反らせずにいると、 隣の友達に笑いかけた拍子に横顔が見えた。 紛れも無くさんだった。 驚いて一瞬足が止まりそうになったが、隣の三郎が不審な目でこちらを見ているのに気付いて慌てて足を動かした。 もう一度さんに視線を移せば、楽しそうに友達と話をしている。その横顔が眩しくて視線を下に落とす。 同じクラスじゃないのが悔やまれる。今じゃ話す機会は無い。 体育の授業の片づけを先生に頼まれ、ようやく終わって下駄箱に向かった時には、とっくに今日一日の授業が終わったことを 告げるチャイムが鳴った後だった。もう少し早くここに来ていたらきっと人で溢れていただろう。 グラウンドの土がたくさんついてしまってる靴を地面に叩いて粗方の土を取ってから上履きに履き替える。 熱の引かないうちに着替えを更衣室で終えたので制服がすごく暑い。暑がりのハチなんか前を全開に開けて中に来ているTシャツが丸見えだ。 制服の首のところを持って、少しでも風を起こそうとしてみるけどあまり効果はない。 今日これからの予定を話し合っていると、視界の隅で何かを捕らえた。何とはなしにそちらに視線を向けて驚く。 「ごめん。先行っといて」 「え?」 何故かということも告げずにそれだけ言うとハチと兵助と勘右衛門は不思議そうな表情を浮かべた。 その中で一人、三郎だけはその表情を変化させなかった。 「じゃあ行ってるから。行くぞ」 「うん」 どういうことか分からずにその場で動かない三人の背中を三郎が何でもないような顔で押した。三人もそうすれば 歩かないわけには行かずに何が何か分からない様子で三郎に連れて行かれた。途中三郎と視線が合って、片方の口角 を上げた意味ありな笑みを向けられた。僕はそれに右手を上げて答えた。三郎には何も言って無いのに、(なんせ僕自身気付いたのは最近だ) 何かを分かっているかのようだった。三郎はそういう不思議なところがある。 「わ、...不破くん」 僕が玄関ホールに居たことに、というよりも人が居たことに驚いた様子でさんが声を上げた。 短くなった髪が肩のところで弾む。 「久しぶり、さん」 僕がここで君を待ち伏せしてたなんて知らないだろう。 僕もそれを知らせるつもりは無い。当たり障りの無い挨拶から まずは会話を始めた。 「久しぶり。クラス変わったら全然会わないね」 全然会わないけれど会おうと思えば簡単に会える距離だ。それをしないのは僕たちの関係が希薄なものであると 改めて言われているかのようだった。僕の勝手な被害妄想だとはわかっているけれど...。 さんは僕が声を掛けたことに最初は驚いた様子だったが、今はちょっとだけ口角を上げてあの澄んだ声で答えてくれる。 上履きを脱いで靴箱の中に入っていた茶色いローファーと交換しているさんを眺めながら、僕は予め考えていた話題を口にした。 「新曲出たね」 パッと振り返った弾みで柔らかそうな髪が宙に舞って、目を輝かせたさんと目があった。 またたきをした瞬間、瞼の裏に一瞬、あの日の 逆に言えば他に共通の話題は僕たちの 間には無い。正確に言えばあるのかもしれないけど、まだそれを知るほどにさんのことを知らない。 「うん。不破くんは買った?」 そのCDを手に取って真っ先に君のことを思い浮かべた。なんて言ったらさんはどう思うだろう。 実行する気の無い...言ってしまえば意味の無い“もしかして”を想像する僕はきっととても滑稽だ。 「買ったよ。さんももちろん買ったんだよね?」 「もちろん」 さんはちょっと得意げに力強い頷きを何度も返してくれた。新しいさんの一面に僕は嬉しくなって、ちょっとだけ笑った。 そんな僕を見てさんが小さく笑う。順調な会話に僕は内心すごく舞い上がっていた。あの日と比べれば順調すぎるほどだ。 そのとき、誰も通りかからなかった玄関ホールに一人の男子生徒が歩いてきた。僕たちをちらりと横目で見たかと思うと、 そのまま横を過ぎてく。それが切欠になったらしく、妙な間が空いてからさんが控えめに声を上げる。 「...じゃあ、そろそろ帰るね」 「あ、そうだね。ごめん、引き止めちゃって」 「全然」そう言いながらさんは右手にローファーを持って歩いていく。 靴を履くさんの後ろ姿を見つめていると、玄関に入り込んできた風がさんの髪をさらりと撫でていった。 ふわりと肩までの長さになった髪が靡く。そこで僕は本来の目的を思い出した。 「あっ、」 僕が突然声を上げたので、さんは足を止めて振り返った。不思議そうな目が僕だけに向けられていることに少し緊張する、 それと同時に優越感らしきものも確かに感じた。小さくばれないように息を吸う。 「髪、似合ってるね」 随分と短くなった髪はさんにとても似合っていた。トレードマークとも言えた長いきれいな髪もさんにとても似合っていた。 それをばっさりと切ってしまったことは残念に思う。あそこまでの長さを切ろうと踏ん切りをつけた理由がなんなのか知りたいと思うけれど、 それを尋ねることは今はまだ早い気がした。今はただ純粋に新しい髪形がさんにとても似合っていると伝えたかった。 返答を待つ少しの間に僕はだんだんと緊張してきた。言葉を口にした時にはそこまで緊張を感じていなかったのに、指先がぴりぴりする。 「...ありがとう」 やがて照れくさそうにさんがはにかんだ。少しだけ赤くなった耳が髪の隙間から見える。それが僕は嬉しくって、同時に照れくさかった。 だけどすぐにそれはさんがあの日のように手で触れたことによって隠れてしまった。 身を翻して走っていく後姿を見つめながら僕は細い息を吐いて胸にじわじわと暖かいものが湧き上がってくるのを噛み締めていた。 (20120623) |