|
私が先生を初めて見かけたのは、たぶん廊下かどこですれ違った時だったと思う。 先生、と呼ぶにはとても若く見える人に私はあんなに若い先生が居るんだ、なんておもしろみの無い感想を思った。 首から下げられたネームプレートに視線を移そうとした時、ばたばたとやかましい足音が複数聞こえたかと思うと、 私の視界を遮るように女の子達が現れてネームプレートを隠してしまった。 「せんせー、昨日あそこのスーパーに居たでしょ!」 舌足らずで甘えたような“せんせー”を聞いただけでもその子が先生にどういった感情を抱いているのか想像がついた。 くすくす笑う女の子たちに囲まれた先生は困った顔をして笑っていた。 「あそこのスーパーってのはどこのスーパーだ?」 「誤魔化そうとしても無駄だよ、せんせー」「いくつも行ったからどこのスーパーか分からないんだ」「えー! せんせースーパー梯子してんの?」 「なんで?」「そりゃ...安い物がスーパーによって違ったからだ」「えー、なんかお母さんみたい!」「あれじゃん、主夫じゃん」 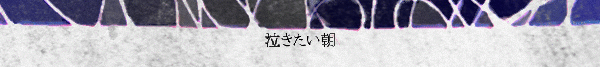
それから一年間、私は先生を廊下や職員室なんかで見かけるぐらいだった。それがガラリと変わったのは、進級して 新しい担当の中に先生が居たからだ。現国:土井、新しく配られた時間割の中にその文字を見つけた。 土井先生と言えば、あのスーパーを梯子する人しかこの学校には居ない。 私は時間割を透明なクリアファイルに挟んで見つめた。今日から数えて一番近く現国の授業が行われるのは二日後だった。 だからなにってことも無いのだけど、私はそれだけを確認してから机の中にファイルを直した。 土井先生という人は生徒達に慕われる要素をたくさん持った人だということに気付いたのは何度も授業を重ねればわかることだった。 女の子達が先生を取り巻いている姿は時々見かける光景だった。それどころか男の子も廊下ですれ違えば先生に何か軽口を叩いている。 生真面目で、だけど冗談が通じないわけじゃない。その上に私たちの事をよく考えてくれるとくれば人気が出るのも頷ける。 他の先生たちに比べて年が近いということもあって親しみやすいのもそれらの要素を引き立たせて見えるのかもしれない。 テスト明けの学校を私は風邪を引いて休んだ。二日休んで学校に行った時にはもうテストは粗方返って来たと友人 から話を聞いていた。授業が始まる毎に名前を呼ばれ、テストを返却され、遅れて一喜一憂を繰り返していた私の手元には一気に答案 用紙が返って来た。採点を間違っている場合もあるから友達に聞いてくれという先生もいれば、正解の書かれた回答用紙をくれる 先生も居た。それを普通の授業と同時に進行して、それも何度も繰り返していたので私はいい加減疲れていた。 自分が風邪を引いたのが悪いといえばそれまでだけど、私だって好きで風邪を引いたわけじゃない。 現国の授業でも同じことが繰り返されるだろうことは簡単に想像できた。 「」 立ち上がって教卓の前に行くと先生が二つ折りにした紙を手に持っていた。それが何であるのかは先ほどから繰り返してる 、テンプレと言ってもいい一連の流れでわかっていた。 「この間休んでた時に返却したテストだ」 「はい」 「これは回答な。採点を間違ってたらまた言ってくれ」 答案用紙と一緒に、おそらく先生の直筆で書かれたと思われる解答のコピーが手渡される。視線をそこに落としながら頷く。 教室の中はまださっきまでの休憩時間の余韻が残っているように騒がしかった。 「風邪はもう大丈夫か?」 踵を返そうとした時に掛けられた言葉が思ってもいなかったものだったので、咄嗟に返事が喉に詰まった。 吃驚しながら顔を上げれば土井先生が優しげな表情を浮かべて私を見ていた。 「あ、はい...」 声が喉に絡むようにかすれた声が出た。けれど風邪はもうだいぶんよくなっていたはずだ。二日間ほとんど寝て過ごした おかげで今日は随分と調子が元に戻ったと思っていたのに...。 「そうか」 土井先生はそれだけ言ってまた笑った。私は早足で自分の席に座って、握っていたテスト用紙を机の上に置いた。 テスト用紙は皺がたくさんついてぐしゃぐしゃになってしまっている。唇を引き結んでそれらの皺を引き伸ばしていると、友達が隣の机から 「点数どうだった?」とこっそり聞きにくる。「ん、まだ見てない」答えながら皺を引き伸ばす作業を中止して、 二つ折りにされた紙を開いているところで先生が授業を開始する声が聞こえたので、私は隣からの視線に気づかないふりをして テストの見合わせを始めた。 先生が間違えて正解にしている本当なら不正解の回答。 だけどもう一つ、先生が間違えて不正解にしてる正解の書かれた回答。どちらも点数は同じだ。 プラスになってマイナスになる点数は結局変わりのないもので...この行動の意味を自分に問いかけた。 正解の方だけを申告すればテストの点数は上がることになるな。なんて私の頭にずるい考えが浮かぶ。 「先生」 「...もしかしたら採点間違ってたか?」 教室を出た先生の後姿に声を投げかければすぐに振り返ってくれた。そして私の手に握ってある紙を見なくても先生は 私が声を掛けた理由を当てて見せた。頷いて答えながら手に持っている用紙を開いて先生に見せる。 私よりも背の高い先生は自然と腰を屈める体勢で私の持っている用紙を覗き込んできた。先生は両手で教科書や 資料や出席簿なんかを抱えていたので、受け取ることが出来ずに腰を屈めたようだった。近い距離に腰が引けそうに なるのを、それは不自然な行動だと自らに言い聞かせてその場で踏みとどまった。だけど馬鹿みたいだけど顎を引いて出来るだけ距離を取った。 「あの、ここが...」 「あぁ、本当だ。すまないな」 ピン、と跳ねたチェックマークのようなバツ印を指さし、それを見た先生はすぐにそれが採点違いだと気付いたらしい。 もう一枚持ってきていた解答の書かれた用紙を広げる必要は無かったようだ。 先生は用紙を受け取ると片手に荷物を纏め、その中からペンを探しているようだった。どう見ても荷物が邪魔になって いるのが見て分かり、手ぶらに近い状態の私は差し出がましいかもしれないとは思いつつ声をかけた。 「あ、あの」 荷物を持つという意味で手を差し出せば、先生はすぐに意味を読んで、私の手の上に教科書や出席簿を置いた。 先生の体温が移ってしまったらしいそれらは暖かかった。 「ありがとう」 確かな重みと共に先生が屈託無く笑ったので、私は口の中でもごもごと訳のわからない返事をした。 先生が担当してる生徒の評価が全て書き込まれてるだろう革張りの手帳のようなそれを下敷き代わりにして 先生は答案の表面に跳ねていたチェックマークの線を利用して無理やり丸に変えてしまった。 そのままペン先が点数のところに移動しようとした時に私は慌てて声を掛けた。 「あの!」 「ん?」 不思議そうな表情を浮かべる土井先生を見て、私はさっき頭をちらついたずるい考えを思い出してバツが悪くなった。 視線を先生から答案へと向け、手の中に抱えたぬるい温度を保つそれらを両手から片手に抱えなおした。 一本突き出た指を用紙の上に滑らせる。 「えっと、ここも間違ってて...」 「え?」 「...これ、不正解なのに先生が間違って丸をつけてます...」 「あぁ! 本当だ!」 私がおそるおそる指した先を見て先生は驚いた声を上げた。「ダメだな」独り言のように呟かれた言葉にパッと視線 を上げるとこっちを見ていた先生と目があった。眉尻が下がって困ったように笑っている。よく見る笑い方だ。 「急いで採点したからミスが多い」今度は私に対しての言葉だった。私の文字の上に書かれた赤い丸の上にチェックマーク が入れられた。 「...けど点数はどっちも同じなので結局点数に変わりはないです」 自分で言っておいて、これはフォローのつもりなのかと問いたくなった。何のつもりで口から滑り出たのか知らない けれど、聞きようによってはさっきの先生の言葉に対してのフォローにも聞こえる。必要の無い言葉だった、 自意識過剰な言葉だったと羞恥心がじわじわと襲い掛かってきた。それらに気付かないふりをして私は用紙の上で止まった ままのペンをじっと見つめた。しばらく止まっていたペン先が不意に動いたと思うと、点数が記されたそこに移動する。 そのままペンは書かれていた数字に横線を二本引いたと思うと、それよりも一つ大きな数字が書き加えられた。 「え...」 土井先生は私の言葉を聞いていなかったのだろうか。戸惑いながら視線を上げると、先生は目尻を柔らかく緩めて笑っていた。 「おまけだ」 先生はそう言うと、用紙をまた二つ折りにして返してくれた。それから下敷き代わりにしていた革張りの手帳のような それを開いて何かを書き込む。この状況から想像がつくけど、私の点数を書きかえたのだと思う。 けれど腑に落ちなかった。何でおまけを私にしてくれたのか。 それが顔に出ていたのか、先生は顔を上げて私の顔を見るとおかしそうに笑った。それから私の手の中にあった教科書諸々を お礼と引き換えに引き取っていく。軽くなった手の中には教室を飛び出した時と同じように紙が二枚だけ残った。先生の体温が移りようの無いぺらぺらの紙だけ。 休憩時間も半ばを過ぎている廊下にはいつの間にか生徒で溢れていた。 その光景を見た途端、唐突に耳が機能したように全ての音を拾い上げ始める。さっきまでは土井先生と私を隔離するように 薄く膜が張っていたのかと思うほど静かに感じていたのに。休み時間特有の音がうるさくて少しだけ眉間に皺がよってしまう。 「あ、このことは誰にも言うんじゃないぞ」 最後にこっそり囁かれた言葉に私は呆けたように固まった。先生は停止した私に悪戯っぽい笑みを浮かべて見せ、 腕時計に視線をやってから吃驚した様子で慌てて去っていった。 がやがやと音で溢れかえる廊下の隅での秘密のやり取りを私はどうしたって意識せずにいられなかった。 それからの私はこっそり現国の時間がやってくるのが楽しみだった。 黒板の前に立つ土井先生はいつだって先生の顔をしていたけれど、あの日廊下の隅で見せてくれた先生の少しだけ 子供っぽい表情を私は何度も擦り切れるほど思い出してはその度に口元を緩めていた。いつもは見ることが出来ない先生の 一面を私は見ることが出来たのだ。 それは特別な匂いを放って私をいい気分にさせてくれた。 廊下で擦れ違うときの挨拶「おはようございます」「おはよう」ただそれだけのやり取りにも私の心は弾んだ。 土井先生もあの時の秘密のやり取りがあったからか、それとも日頃の私の挨拶がよかったのか、たくさんの生徒が 居る中で私のことをちゃんと認識してくれているようだった。私が先生の存在に気付かなかった時も、向こうから声を かけてくれることもあった。 私は徐々に胸の中で何かが成長していくのを確かに感じていた。 授業終了と共に男の子達は次の時間は体育だからとはりきって教室を出て行く。そんな中、私たち女の子はのんびりと いつもと同じ休憩時間を過ごしていた。担当の先生が出張だとかで次の時間は自習だ。体育は男子と女子で分かれて 行われるのが常だったので、男子は通常通りの体育が行われるが、私たち女子はのんびり出来るのだ。 半数以上が居なくなり、がらんとした教室内で私は友人といつものようにおしゃべりしながら先ほどの授業の片づけを している様子の土井先生をちらちらと横目で見ていた。今日は資料を使っての授業だったので荷物が多いようだ。 教室に来るときは誰かを捕まえて二人で運んできていた物を一人で持って帰れるのだろうか。 “手伝いましょうか?”そう声を掛ければいいのは分かっているのにどうしても難しく感じてしまう。 ちらちら横目で先生を見て、話を半分聞き流していたので友人もすぐに私の意識が他所にあることに気付いた。 「土井先生、荷物一人で持てるのかな?」 「だね。ちょっと多そうだよね」 二人分の視線に気付いたのか、俯いていた先生が顔を上げた。突然の動きに私は咄嗟に反応できなかった。 思いがけず目が合ってしまい、私は丸まっていた背中を反射的に伸ばした。それを見て先生が笑ってから、こっちに向かって手招きする。 「、ちょっと手伝ってくれないか?」 「あ、え、はい...」 「あーあ、目つけられちゃったね」友達は私が先生の手伝い係りに任命された事に楽しそうに笑った。気の毒、とでも 言いたげな物言いに私は苦く笑って見せたけれど、本心は表情とは裏腹だった。軽い足取りで、けれど走らないよう微妙にさじ加減しながら先生の元へと歩く。 「悪いが資料を運ぶのを手伝ってもらえないか?」 「これですか?」 慣れて最初の頃よりは先生と話すことに緊張しなくなっていた私は頷きつつ、進んで一番前の机の上に置かれた たくさんの資料を指差した。結構な高さに重ねられたそれらはきっと重いだろうことは予想がついた。 「そっちは私が持つからこっちを頼む」 そう言って渡されたのは、いつも先生が持ち歩いている授業セットとくるくる巻かれて一枚から一本の姿に変わった 大きな紙だ。さっき黒板に張って実際に使われている場面を見たので、中には何が書いてあるかは分かっている。 「よっ、いしょ」 先生が年に似合わない掛け声と共に資料を持ち上げる。「せんせー、じじくさい」私たちのやり取りを見てた女の子 が笑いながら指摘する。それに先生は「いつかはお前たちもこうなるんだ」なんて軽口で応戦した。 資料の山を抱えた先生は首のところまで隠れてしまいながら歩き出した。私は慌てて先に回り、教室のドアを開けた。 「ありがとう」 資料の山から顔を覗かせて先生が笑う。私は口に力を入れて多分笑って返した、と思う。 騒がしい廊下を視界に先生の背中を入れながら歩く。先生は重い荷物を持っているのに足元がふらつく事無く、しっかりと した足取りで国語準備室までの道のりを進んでいく。対して私の手にはそう重くは無い荷物が抱えられている。 大きさばかりが邪魔になるスカスカの一本になった紙を、私はまるで城を守る門番が槍を持っているようにして運んだ。 ときどき珍しげな視線を感じながら、それでも真っ直ぐ前を向いて先生の背中について行く。 「...先生、重くないですか?」 「重いぞ。腕が千切れそうだ」 一緒に居るのに会話をしないのもどうかと思いきって話しかけてみれば冗談なのか本気なのか分からない言葉が返って来る。 声は苦しそうではないけれど、重くないわけがないのはその腕に抱えている山になっている物を見ればわかる。 ...わかってるくせに声を掛けたのだけど。 「あ、じゃあ私ちょっと持ちます」 「え! いや、大丈夫だ」 断られる事は予想がついていた。腕が千切れそうなほど重いと言っていたのに、私の言葉を聞いて慌てた様子の先生を 無視して大きくてかさばるわりに軽い資料を腋に挟み、先生が運ぶ資料の山に手を伸ばした。いつもならこんなに積極的にはなれなかったと思う、けれど今日はそういう気分だった。 教室の中のたくさんの中から土井先生は私を選んでくれた。それが私を浮かれさせて、普段では出来そうにない行動を取らせた。 先生も今まで見せたことが無い私の積極的な一面に驚いているようで、私は悪戯が成功したかのように胸がすっとしたのを感じた。 強引に先生の抱える山から数冊の資料を持ち上げ、手に既に抱えていた先生の授業セットの上に重ねる。 「ありがとう」 今日二度目の“ありがとう”に私は照れくさくなって唇に力を入れた。 「よいしょっと」 どさっと机の上に資料を置いてから先生は、しまった。と言いたげな顔をした。さっきじじくさいと指摘されたばかりなのに また言ってしまったからだろう。「もうこれは癖だな」と、先生は頭をかいて苦く笑った。 じじくさいと言われた事を気にしているらしい先生が面白くて私はつい吹き出してしまった。 「あ、笑ったな。そういうも人事じゃないからな」 先生は照れたようでもあったし、何だか楽しそうでもあった。他の先生はみんな出払ってるいらしく、国語準備室の中は 私と土井先生の二人だけだった。 二人きりだった。 「だって、先生、じじくさいって気にしてたんですね」 おかしくって口を両手で隠しながら再度笑い声を上げると先生も眉尻を下げてしょうがないと言っている様に表情を緩めた。 部屋の前を何人かがバタバタと走って行く足音が聞こえた。部屋の中が静かなのでその音は思ったよりも大きく響く。 私は声を押し殺すために両手で口を押さえた。何となくこのやりとりを誰にも聞かれたくなかった。 「そんなに笑ったらコレは無しだな」 「え?」 また静けさを取り戻した部屋には先生の声がよく響いた。口を両手で押さえて俯いていた状態から顔を上げると、 先生が右手に何かを握っているのが見える。“コレ”とは一体何なのか、私の興味は自然と先生の右手のものへと向く。 私の素直な目の動きに今度は先生がおかしそうに笑った。 「手伝ってくれたし、そんな顔をされたら渡さないわけにはいかないな」 そう言った先生は右手を握ったまま私の前に持って来た。私は首を傾げつつも胸の前で両手を受け皿のようにした。 ぽとん、手の上に落とされたのは個包装の飴玉だった。昔からある花の絵が描かれた飴だ。どこか懐かしい雰囲気の それは自分で買うのだったらまず手を出さないものだ。じっと手の中の飴に視線を落としていると、頭の上からちょっと焦ったような「嫌いだったか?」と言う声が聞こえた。 「好きです」 ホントは好きかどうかなんて食べたことが無いから分からなかった。けれど、私はこの飴をきっと好きだと確信していた。 「そうか」先生は私の返答にホッとした様子で笑う。私はその姿を見つめながら息を詰めた。 私がこの飴が好きだったと言ったから先生はホッとしている。その事実が何か言い知れぬ感情を呼び起こしそうだった。 「助かったよ。ありがとう、」 今日三度目のありがとうを受け取って私は心の中で律儀な人だと呟いた。 「またくれるなら手伝ってもいいですよ」 まだ私の気分は浮かれたままだった。それどころかさっきよりも拍車を掛けて浮かれた気分で、地に足が着いていないようなふわふわした変な感じで、気分が高揚していた。 だからいつもだったら言えない小生意気で尊大な台詞を言う事だって出来た。 先生は生意気な口を利いた私に意外そうに目を丸くして、だけどすぐにあの優しい顔で笑った。 「生意気だな。これは成績にも響かせないといけないなぁ」 「...え! すいません」 すぐさま謝ると先生は声を立てて笑った。次いであの日に一度見ることが出来た少しだけ子供っぽい笑みが目に映った。 べりっと一瞬、“先生”の顔が剥がれ落ちたのを私は確かに見た。教卓の前で授業をする先生の顔とは違う、プライベートな顔。 あの日のように周りの音が全て遠くなる現象が起こった。変わりに耳には心臓が脈打つ音が聞こえる。 「冗談だよ」 先生はそう言って私の呆けた顔を楽しそうに眺め、また先生の顔をぺたりと貼り付けた。 「さぁ、休憩が終わるぞ」 そう言った土井先生の顔はすっかり“大人”で“先生”のものになっていた。黒板の前に居る時に見る、見慣れた顔だ。 私は先生に貰った飴玉を一つ右手に握りながら早歩きで教室へと戻ろうとした。髪をあえて耳にはかけずに、顔を隠すように して進んだ。どくどくと心臓が脈打つ音で頭がくらくらする。その時、次の時間は自習だったことを途中で思い出し、そう急ぐ理由もないと思いなおしてトイレへと駆け込んだ。 無人であることを目視し、洗面台に一直線に走って、蛇口を捻って水を出した。そこで右手に握っている存在を 思い出して、ポケットにそっと飴を落とす。少し馬鹿になってる蛇口は回した分に伴わないまどっろこしい量の水しか吐き出さない。 その中に両手を突っ込むと、心地いい冷たさが手を冷やした。自分が何でこんなことをしているのか分からないまま私は水に手を浸して、 ジョボボボボと恐ろしげな音をたてて排水溝に水が吸い込まれる音を聞いていた。 やがて聞こえたチャイムの音に顔を上げるとひどい顔をした自分が壁に備え付けれた鏡に映った。 泣き出しそうだけど嬉しそうでもあるよく分からない顔で、おまけに顔がみっともないほど赤かった。 すっかり冷えた手を適当に振って水を払ってから熱い頬に当てる。火照った頬にはそれが冷たくて気持ちいい。 すでに静まり返っていた廊下を、足音を潜めて歩きながらポケットに手をつっこんだ。 きっとこの飴はとても甘い。 → (20121021)続きます |